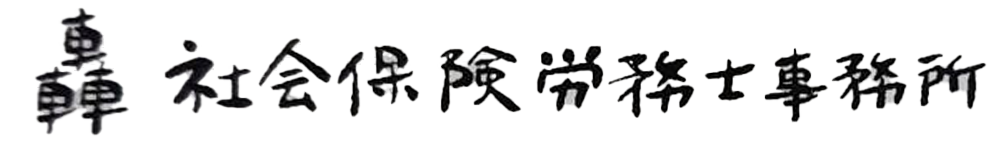社員が入社した時の手続き
社員が入社した時の手続き
大分市にあります轟社会保険労務士事務所 代表 轟憲人です。
新社会人は不安と期待を胸に、そのほかの社会人は年度末の忙しさに目を回している時期かと思います。
今回は社員が入社した時の手続きについて簡単にご説明したいと思います。
手続きはいくつかあります。
マニュアル化している大企業は担当者がそれぞれ分かれているかもしれませんが、一般の中小企業は1人ですべて行ない、法改正などあると抜けたりする箇所も出るかもしれません。
手続き前には一度、厚生労働省のホームページを見て確認をしましょう。
まずは、 労働基準法関係の手続き です。
・就業規則に定める書類の提出
「住民票記載事項証明書」「卒業・成績証明書」「入社誓約書」「身元保証書」などを、就業規則に定める期日までに提出してもらう。
・労働条件通知書の交付
労働基準法の定める絶対的明示事項(必ず明示しなければならない事項)、相対的明示事項(定めがある場合は明示する事項)を書面により明示しなければならりません。(投稿記載)
空欄を埋めるだけで「労働条件通知書」が作成できるモデル様式(一般労働者用:常用、有期雇用型 / 短時間労働者・派遣労働者用:常用、有期雇用型)が、厚生労働省HPからダウンロードできるので利用するとよいでしょう。
そして、 雇用保険・社会保険関係の手続き です。
・「年金手帳」「雇用保険被保険者証」の提出をしてもらう。
これらを紛失している場合は入社する直前に被保険者として使用されていた事業所の名称、所在地等を記載する必要があります。
・「健康保険の被扶養者」の有無の確認をする。
(被扶養者の氏名のフリガナ、性別、同居・別居、所得の確認を忘れないように)
最後に 税金関係の手続き です。
・住民税
前職の有無、入社年の住民税納付状況によって手続きが異なるので注意が必要です。
・所得税
給与所得者より「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、前職がある場合は「給与所得の源泉徴収票」を提出してもらい、「源泉徴収簿」を作成します。
なお、手続きの際は本人を含め被扶養者すべてのマイナンバーも必要となります。
さて、雇用保険に関する手続きでは下記のことに注意をしましょう。
対象者が65歳以上のとき
65歳以上:雇用保険に加入しない。
⇒ただし、65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳に達した日以降の日においても
引き続いて雇用されている者(高年齢継続被保険者)や短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く)。
⇒年金受給権がある場合、配偶者は60歳未満でも国民年金第3号被保険者になることができない。
70歳以上:厚生年金に加入しない。
75歳以上:健康保険に加入しない(後期高齢者医療制度に加入)。