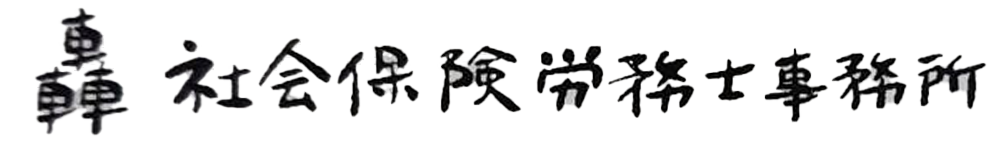今回は、労働保険の年度更新の手続きの流れや申告書の書き方などについて記入例も参考にしながら詳しく解説していきます。
年度更新について 1
労働保険料は原則として毎年6月1日から7月10日までの間に「年度更新」という手続きによって、当該年度分の納付と前年度分の過不足の精算を同時に行うことになっています。
年度更新とは
労働保険料は社会保険料のように毎月納付するものではありません。
労働保険料は毎年1回、6月1日から7月10日までの間に確定保険料と概算保険料の申告、納付及び精算の手続きを同時に行うことによって納付することになっています。この手続きを「年度更新」と言います。
- 確定保険料の申告、精算
- 概算保険料の申告、納付
確定保険料の申告・精算
対象労働者の前年度(4月1日から翌年3月31日)の賃金総額から確定した労働保険料を計算して申告、納付します。
算出された確定保険料の額が前年度に納付した概算保険料の額よりも多ければ、当該年度の概算保険料とあわせて追加で納付することになります。
一方、確定保険料の額が前年度に納付した概算保険料の額よりも少なければ当該年度の概算保険料に充当するなどになります。
概算保険料の申告・納付
対象労働者の当該年度(4月1日から翌年3月31日)の見込み賃金総額から労働保険料を概算して申告、納付します。
ただし、上記の確定保険料の精算によって納付額がさらに多くなる場合や、反対に納付の必要がなくなり還付を受ける場合もあります。
建設業などの年度更新
建設事業や農林水産の事業などは「二元適用事業」とされ、労災保険料と雇用保険料を別々に申告、納付することになっています。また、建設事業のように事業の期間が予定されている事業は、「有期事業」とされ、労災保険料と雇用保険料は事業開始時に納付し、事業終了時に清算することになっています。
では、必要な書類はどんなもので、何を提出すればよいのでしょうか。
・労働保険概算保険料申告書
対象となる年度の見込み賃金の総額を記入して申告するのが、労働保険概算保険料申告書です。見込み賃金を基に労災保険と雇用保険を算出し、申告書に記入します。
他にも雇用している従業員数や雇用保険に加入している従業員数、保険年度中に満65歳以上となる高年齢労働者数などを記入しなくてはなりません。
・確定保険料算定基礎賃金集計表
実際に支払った賃金総額を基に算出するのが確定保険料です。
確定保険料算定基礎賃金集計表は確定保険料を計算するための、賃金総額の集計表となります。
雇用保険の加入条件を満たし、労災保険、雇用保険、高齢者の人数と賃金総額を集計して記入します。
賃金に関しては注意が必要です。
・保険年度中に支払いが「確定」した賃金が対象
労働保険料は対象となる保険年度に支払った賃金総額で算出しなくてはなりません。
社会保険料や税金は賃金の支払い日で計算すれば良いですが、労働保険料は締日で計算するため、年度末に締めた賃金が翌月払いになっていたとしても集計対象となります。
以上、大まかに年度更新について説明しました。
次回はより詳しくお伝えできたらと思います。
厚生労働省のホームページ
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/kousin.html