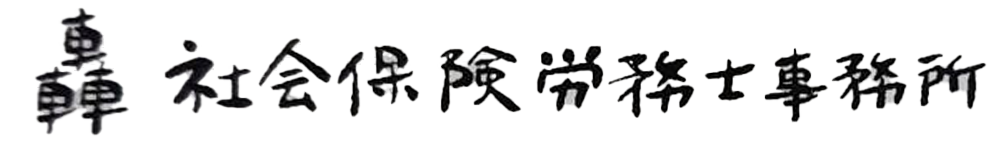年度更新について 2
ホーム スタッフブログ
建設業における労働保険の年度更新
今回は建設業の申告書作成時の注意点をお伝えしたいと思います。
一括有期事業報告書の作成
対象となる事業
下記に該当する事業が、報告書に記載する対象事業です。
・元請負により実施した工事
・請負金額が1億8千万円未満の工事
・概算保険料額が160万円未満の工事
・令和5年度中(令和4年年4月1日~令和6年3月31まで)に終了した工事
記入事項
・事業の名称、事業場の所在地、事業の期間
・請負代金の額(契約金額)
・請負代金に加算する額(支給財の価格相当額+貸与物の賃貸料や損料相当額)
・請負代金から控除する額(「機械装置の組立又は据付の事業」の機械装置)
⇒以上を表に記載し、請負金額を算出し、労務費率から「賃金総額」を算出します。
・事業の種類・開始時期により、労務費率・保険料率が異なるため、「事業の種類」「事業の開始時期」に分けて記載
多くの場合は請負金額より算定します。
・事業開始の時期により、消費税額の取り扱いが異なるため、請負金額の算出に注意が必要
一元適用事業と二元適用事業
建設業の労災保険について理解する上で、一元適用事業と二元適用事業の違いを理解しておく必要があります。一元適用事業と二元適用事業のそれぞれの意味は、次のとおりです。
| 分類 | 定義 | 業種 |
|---|---|---|
| 一元適用事業 | 労災保険と雇用保険をまとめて申告・納付する事業 | 下記以外 |
| 二元適用事業 | 労災保険と雇用保険を別々に申告・納付する事業 | 建設業や農林漁業など |
つまり建設業は、労災保険と雇用保険を別々に申告・納付する二元適用事業に該当します。保険の成立手続きについても、一元適用事業とは手順が異なるため、注意が必要です。
一括有期事業と単独有期事業の違い
建設業の労災保険について理解する上で重要となるのは、一括有期事業と単独有期事業という2つの分類です。
建設業の工事では、工事期間が終了して建築物が完成すると、事業が終了するのが一般的です。工事のように終了時期が決まっている事業は、「有期事業」と呼ばれます。(建設業以外の終了時期が決まっていない一般的な事業は、「継続事業」と呼ばれます)
有期事業には、状況に応じて一括有期事業と単独有期事業という2つの分類が存在するため、それぞれどのような違いがあるのか解説します。
一括有期事業とは
下記に当てはまる場合は、一括有期事業として労災保険に加入できます。
- 同一の事業主であること
- それぞれの事業が建設業または立木の伐採の事業であること
- それぞれの事業の概算保険料が160万円未満であること
- 建設業は、それぞれの事業の請負金額が1億8,000万円(税抜)未満であること
- 立木の伐採の事業は、それぞれの事業の素材の見込み生産量が1,000㎥未満であること
- それぞれの事業の労災保険率が同じであること
なお一括有期事業に該当する可能性があるのは、建設業以外には林業(立木の伐採の事業)もあります。
一括有期事業の適用者は年度更新時に書類を追加で提出
一括有期事業の適用を受けた場合、労災保険の年度更新時に、下記2つの書類を追加で提出することになります。
- 一括有期事業報告書
- 一括有期事業総括表
年度更新時には提出を忘れないよう注意しましょう。
単独有期事業とは
単独有期事業とは、一括有期事業に当てはまらない有期事業を指します。
単独有期事業は、労災保険料を納付するタイミングが、継続事業や一括有期事業とは違います。労災保険が成立した日から20日以内に、工事期間中の概算保険料をまとめて申告・納付します。
条件を満たせば分納が可能
単独有期事業の概算保険料は、下記2つの条件を見たせば、分納(延納)が可能です。
- 工事期間が6ヶ月を超えること
- 概算保険料の金額が75万円以上であること
なお単独有期事業の概算保険料を分納するためには、事業主による申請が必要となります。
厚生労働省のホームページ、令和6年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/ikkatu-all.pdf