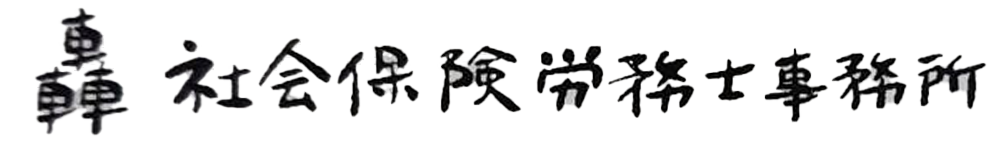『育児・介護休業法』の改正
大分の社会保険労務士、轟憲人です。
今回は2024年5月31日、公布された改正育児・介護休業法について簡単にご説明したいと思います。
れまで支援の中心は「3歳に満たない」子を養育する労働者でしたが、「小学校就学の始期に達するまで」に拡充され、子を育てながら柔軟に働けるような制度の導入が企業に義務付けられます。
以下、厚生労働省『育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内』より、『育児・介護休業法』の改正について抜粋させていただきながらご説明したいと思います。
1つ目
事業主は
・始業時刻等の変更
・テレワーク等
・保育施設の設置運営等
・新たな休暇の付与
・短時間勤務制度
の中から2以上の制度を選択して措置する必要があります。
これはフルタイムでの柔軟な働き方を目標としており、労働者は事業主が講じた中から1つを選択して利用することができます。
2つ目
時間外労働の制限(残業免除)の対象が
3歳に満たない子を養育する労働者→小学校就学前の子を養育する労働者
となり、時間外労働の制限の請求をすることができるようになりました。
3つ目
さらに、3歳に満たない子を養育する労働者に対して育児のためのテレワーク導入が努力義務化されます。
4つ目
また、この看護休暇が見直されます。
主に、小学校就学の始期に達するまでだった対象が小学校3年生終了までに延長されました。
取得自由も病気、けがなど従前のものに
・感染症に伴う学級閉鎖等
・入園(入学)式、卒園式
が追加されました。
5つ目
そのほか
・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になる。
6つ目
・育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に義務付けられる。
従前は1000人超だった公表義務が、300人超の企業へと変更になりました。
これは今後、男性の育児休業取得率の公表も同じように1000人超から300人超へと拡大されていきます。
7つ目
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務となる。
など、計7つの変更点等があります。
以上、今回の改正で大切な部分を簡単にご説明させていただきました。
一件、事業主にのみ負担が課せられるように見受けられますが、これらの原因による離職率が下がれば、長年勤め、ノウハウが身についた人材を手放さずにすむというメリットは大きいのではないでしょうか。