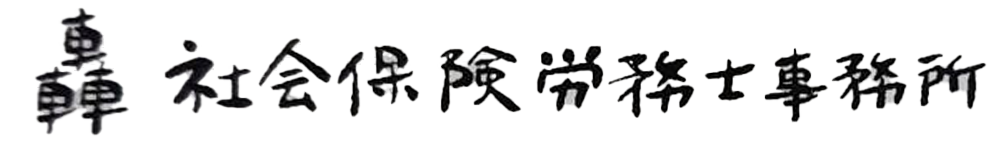年次有給休暇について
5日、年次有給休暇を取得させる義務とは?退職者や休業中の者は?
大分の社労士、轟社会保険労務士事務所代表 轟憲人です。
夏季休暇を促す事業所も増えてきているかと思います。
年次有給休暇(年休)は職員に年5日は取得させないといけないのか。
労働基準法改正(2019年)により、年5日の時季指定義務が制定されてからは、時季指定に悩む事業所も増えているようです。
夏も迫り、夏休みも兼ねて年休を促す事業所も多いことかと思います。
今回は、このテーマについて触れたいと思います。
1.年休の時季指定義務とは
年5日の時季指定義務とは、年休が10日以上付与される労働者に対して
『付与した日から1年以内に、会社が取得時季を指定して年休を取得させなければならない』
というものです。
労働者が自ら年休を請求して取得した場合には、5日の時季指定義務の対象日数から減じることができますので、労働者自ら取得するのか、会社が時季を指定して取得させるのか、いずれにせよ、年に5日は年休を確実に取得させなければならないということです。
では
2.年の途中で退職や休職する者にも5日取得させる必要があるのか
付与日から1年以内に5日取得させなければならないとの原則は分かったものの、それでは、その1年の途中で退職してしまったり、休職に入ってしまったりする者についても、その義務はあるのか?という疑問です。
この点について、実は、労働基準法の条文、施行規則、解釈通達等では何も触れられていません。
ですが、行政の見解では「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」パンフレットに、休職については一応このように触れられています。
■厚生労働省「年次有給休暇の時季指定」
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/salaried.html
Q13 休職している労働者についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要がありますか。
例えば、基準日からの1年間について、それ以前から休職しており、期間中に一度も復職しなかった場合など、使用者にとって義務の履行が不可能な場合には、法違反を問うものではありません。
とあり、年の途中で退職や休職に入ってしまう者に対して義務があるのかどうかなのですがここでは触れられていません。
行政としては、法に根拠がない以上、義務がないとまでは言えないのでしょう。
とはいえ、実際問題として、年途中で退職したり休職に入ったりした者が、結果的に5日取得できていなかったからといって、これを重大な違反として取り沙汰することはないものではないかと解釈したいところです。
もっとも、退職や休職の直前には一定期間の年休を消化している例が多いと思いますので、5日程度の取得であれば、あまり気にしなくとも自然と達成されているのかもしれません。
なお、「年の途中で休職から復職する者(育児休業、介護休業等含む)」については通常勤務している者と同様、年5日の年次有給休暇を確実に取得していただく必要があります。
ただし、残りの期間における労働日が、使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少なく、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合には、その限りではありません。
4月~翌年3月の1年度単位で年休を運用している会社において、休業からの復帰が3月27日に当たり、3月27日から3月31日までの間に5日の年休は無理があるかと思います。
時季指定とは、例えば年度末に半数以上の職員が一斉に年休と取る・・・
などあっては会社が回らないかと思います。
その時にずらして取得してもらうための法律とも取れます。
繁忙期は事業所により異なってくるかと思いますが、その時期に重ならないよう、日ごろから少しずつ年休を消化できるよう努力も必要かも思います。
読み手によって解釈が変わりそうなところがどの法改正でも難しいところかと思いますが、
疑問に思った場合はご相談いただければと思います。